
玉掛け作業に関わる資格を取得するにあたって、資格の正式名称や取得区分を正しく理解しておくことが非常に重要です。
しかし実際には、「玉掛けの資格」とひとくくりにされてしまい、作業内容やつり上げ荷重に応じた資格の違いが十分に認識されていないケースも少なくありません。
私は機械加工技術者として、日々クレーンを用いた製造業務に携わっています。玉掛け技能講習とクレーン運転の業務に係る特別教育を修了し、実務として玉掛け作業を行っている立場から、現場で本当に役立つ情報をお伝えします。
この記事では、玉掛け資格の正式名称や選び方、現場で混乱を防ぐために押さえておくべきポイントを、実体験に基づいてわかりやすく解説します。資格取得を検討している方、職場で指導を行う立場の方にとっても、役立つ内容です。
玉掛けでなくクレーンの資格の正式名称についてはこちらをご参照ください。
玉掛け資格の正式名称は?【結論:作業内容と荷重で異なる】
玉掛け技能講習/特別教育の正式名称と違い
「玉掛けの資格」とひとくちに言っても、実は2種類の正式名称が存在します。どちらも法令に基づいて定められた資格であり、対象となる作業内容とつり上げ荷重によって区分されています。
1t以上の荷を扱う場合に必要となるのが、「玉掛け技能講習」という資格です。これは労働安全衛生法根拠の資格に該当し、登録教習機関での受講と修了証の取得が義務づけられています。講習には実技が含まれ、合図・フックのかけ方・吊り荷のバランス調整といった実践スキルが養われます。
一方、1t未満の荷物を吊る作業に関しては、「玉掛けの業務に係る特別教育」で対応可能です。こちらは企業側に実施義務がある特別教育で、講習自体は社内や外部機関でも可能ですが、内容や修了証の信頼性を重視して外部機関に委託されることが多くなっています。
両者の違いを簡単に整理すると、以下の通りです:
| 項目 | 玉掛け技能講習 | 玉掛けの業務に係る特別教育 |
|---|---|---|
| 対象荷重 | 1t以上 | 1t未満 |
| 実施者 | 登録教習機関 | 事業者または外部講習機関 |
| 修了証 | 必須で発行 | 任意だが多くは発行あり |
| 試験 | あり | 任意 |
補足情報として、500kg未満であれば労働安全衛生法の例外規定に該当し、資格の取得は必ずしも必要ではありません。詳しくはこちらの記事をご覧ください!
なぜ「正式名称の確認」が大切なのか?【現場での混乱を防ぐ】
「玉掛け資格」といった略称は、現場では日常的に使われているものの、正式な講習名を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルの原因になります。私自身も資格取得前、講習内容や名称の違いがよく分からないまま、会社任せに講習を受講した経験があります。
特に注意が必要なのは、「技能講習」と「特別教育」の違いを知らないまま申し込んでしまうケースです。たとえば、実際に1t以上の荷物を扱う現場で働くにもかかわらず、1t未満向けの特別教育しか受けていなかった場合、「現場に出られない」「再度講習を受け直す」といった無駄な費用・手間が発生することもあります。
さらに、外部業者や元請けから「正式な修了証の提示」を求められることもあるため、曖昧な理解のまま資格取得を進めるのは大きなリスクです。講習の案内書や修了証には、当然ながら必ず正式名称が記載されており、これがそのまま履歴書や現場登録にも活用されることになります。
実務に直結する資格であるからこそ、自身や自社の取得するべき資格の正式名称は、実際の業務に影響する重要な知識なのです。
玉掛けの資格制度は2種類【どっちを選ぶべきかは荷重次第】
1t未満の作業なら「玉掛けの業務に係る特別教育」
1トン未満の軽量物をつり上げる作業に従事する場合は、「玉掛けの業務に係る特別教育」を受けることで、法的に業務が可能になります。
この特別教育は、労働安全衛生法により事業者に実施が義務づけられているもので、講習内容には「学科+実技」が含まれます。教育の実施は社内でも可能とされていますが、実際には多くの企業が講習の信頼性と内容の充実を理由に、外部の教育機関へ依頼しています。
私も後述の「玉掛け技能講習」の資格を、クレーン協会にて取得しました。
特別教育という言葉から「簡易な内容」と思われがちですが、荷の振れを抑える方法、安全確認、合図の出し方といった基本動作はしっかり学びます。特に、機械加工の現場では1t未満の玉掛け業務がほとんどになるため、「正式な教育を受けているかどうか」は事故防止や監査対応のうえでも重要なポイントです。
1t以上の作業には「玉掛け技能講習」が必須【体験談あり】
一方で、つり上げ荷重が1t以上の作業に就く場合は、「玉掛け技能講習」の修了が必須です。これは厚生労働省に認定された登録教習機関が行う技能講習に該当し、修了証の提示が義務づけられています。
私自身が受けたのもこの「技能講習」です。クレーン運転の業務に係る特別教育との併合講習だったため、講習期間は5日間でした。学科では法令や力学の基礎、安全管理について学び、実技では実際にワイヤーロープを使った荷の吊り方、荷重バランスの取り方、作業合図の出し方など、実務に直結する内容を繰り返し練習しました。
特に印象に残っているのは実技試験です。10人以上の視線に囲まれて緊張する環境下で声出しによる合図を覚えて順番通りにこなす必要があります。特に安全面に影響する点については現場での事故につながるため、講師にもよりますが、比較的厳しく指導していたのを覚えています。
玉掛けの資格取得の体験談はこちらに詳しく掲載しています!
費用は3万円台前半ほど(地域や教習機関によって異なる)で決して安くはありませんが、「1t以上の玉掛け作業には必須」という法的な位置づけである以上、避けては通れません。
また、現場ではクレーンの操作と同時に行うケースが多いため、私のように「クレーン運転の業務に係る特別教育」と併せて受講する併合講習を選ぶ方も多く、手間と時間を一度に解決できるメリットがあります。
このように、玉掛け資格の制度は荷重によって明確に区分されており、作業内容に応じた正しい資格選びが求められます。
クレーンの資格取得にかかる費用についてはこちらをご参照ください!

まとめ|「玉掛け 資格の正式名称」は実務に直結する知識
玉掛け資格の正式名称は、つり上げ荷重が1t以上か未満かによって「技能講習」「特別教育」と明確に分かれています。
正式名称で言えば、つり上げ荷重1t以上であれば「玉掛け技能講習」、1t未満であれば「玉掛けの業務に係る特別教育」となり、それぞれ講習内容も修了証の扱いも異なります。
どちらの講習も法令に基づく教育であり、現場作業に従事する以上、資格の「名前」だけでなく「区分の違い」や「対象作業範囲」まで正確に理解しておくのが望ましいです。
実際に私が受けた講習では、受講者の中に「1t未満だから資格はいらないと思っていた」と話す方もおり、教育不足による誤解が現場の混乱を招いていることを痛感しました。特に、安全第一が求められるクレーン作業においては、「正式名称を把握し、自分に必要な資格を確認する」ことがスタート地点になります。
また、特別教育であっても実技を含めた講習が推奨されており、信頼性のある外部機関を選ぶことが実務にも直結します。実務経験が浅い場合や初めて玉掛け作業に携わる方は、技能講習の受講を検討しておくと、どの現場でも通用するスキルが身につくはずです。
ぜひ本記事を参考に講習の名称と自分の作業内容を照らし合わせて確認し、最適な資格取得を目指してください。
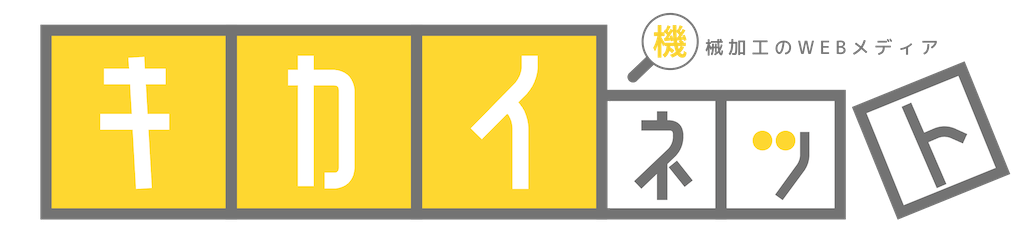


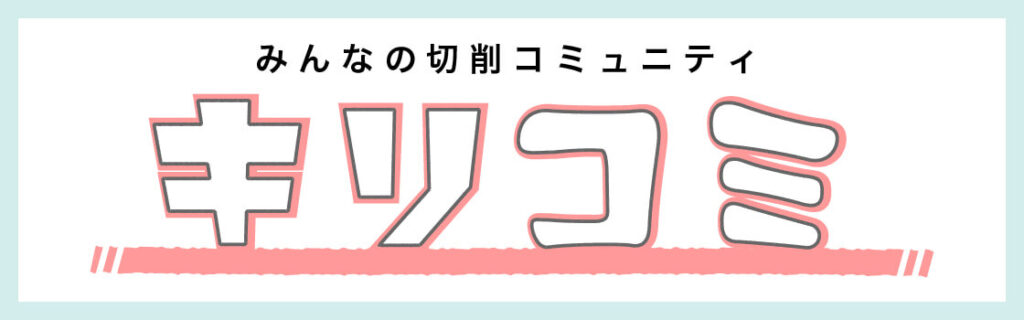
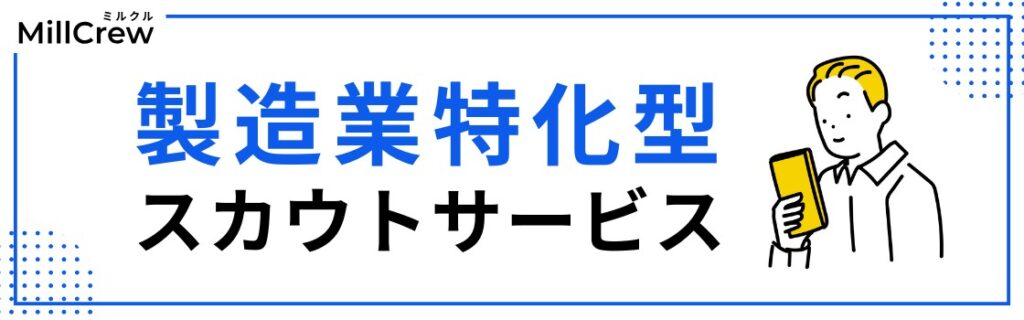

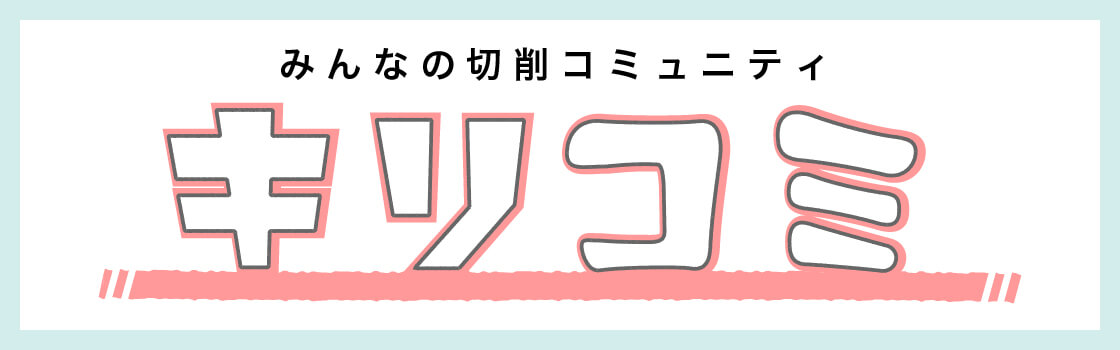




コメント