
寸法測定に欠かせないマイクロメータ。その精度の高さゆえに「測る」だけでなく、「どう保管するか」も非常に重要です。
でも実際には、「ずっと机に置きっぱなし…」「ケースを開けたらサビていた…」といった扱いをしている現場も少なくありません。
本記事では、現場の技術者としての経験やメーカーのマニュアル情報から、私自身が日々実践している正しいマイクロメータの保管方法について詳しく解説します。
測定面の開き方、クランプの扱い、防錆処理、湿度対策、適切な置き場所の選び方まで、すぐにマネできる具体的なポイントを網羅。
「気づいたら精度が狂っていた」「サビが出ていた」――そんな事態を防ぎたい方は、ぜひ参考にしてみてください!
マイクロメータの正しい保管方法とは?
「マイクロを作業台に適当に置いている」という場合でも、精度が求められていないのであればそれでも問題ない場合もありますが、マイクロメータは0.001mm台の測定が可能な測定器。わずかな変形やサビ、ホコリで、精度が台無しになることもあります。きちんと保管しておかないともったいないです。
ここからは、間違った保管で寿命を縮めないために、知っておくべき「正しい保管の基本」を順番に紹介していきます。
精密機器だからこそ重要な「保管の基本」
マイクロメータは、0.001mm単位で寸法を測ることができる高精度な測定器。だからこそ、たとえ目には見えないレベルの変形やサビ、ゴミの付着でも、測定結果に大きな誤差が出るリスクがあります。
一日のおわりに「ちょっとその辺に置いておこう」はNG。まず守るべき基本は以下の3点です!:
- 清掃してから保管する 使用後は、きれいなウエスや、乾いた柔らかい布などで油分やホコリを拭き取りましょう。とくに測定面(アンビルとスピンドルの接触部分)に異物がついていると、正しい測定ができなくなります。
- 防錆処理を忘れずに 長期間保管する場合や湿度が高い環境では、サビ対策が必須です。マイクロメーター用の油を布に染み込ませ、全体に薄く塗ってから保管することで、金属部分の酸化を防げます。油だと何でも良いわけではありません。CRCのような油や、硬い油ではマイクロメーターの動きが悪くなる原因になります。
- クランプせず、ケースや引き出し内で管理する スピンドルを閉じたまま保管するのはNG。詳しくは後述しますが、内部に応力が残り、精度に影響する可能性があります。ケースは衝撃やホコリから守る重要なアイテム。裸での保管は避けましょう。引き出し内などが難しい場合は、ウエスを被せて置くだけでも違います。
- 落下の危険がある場所に置かない マイクロメーターが作業台などから落下すると、衝撃で精度が狂ったり、スピンドルが傷ついてしまう場合があります。少しでも落とす危険がある場所には置かないようにしましょう。
つまり、マイクロメータは「測定だけでなく、保管も精密に」扱う必要があるということ。手間に見えるかもしれませんが、これをルーティン化すれば、トラブル知らずで長く精度を保ってくれます。
測定面は軽く開いておくべき理由
マイクロメータを保管するときは、「アンビルとスピンドルをピッタリ閉じたまま」で保管するのはNGです。
マイクロメータの測定面は、1mmほど軽く開いておくのが正解。開きすぎるとケースに入りませんので、軽く開くくらいが良いです。
ここまでは多くの方がご存知かと思いますが、理由まで考えたことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
軽く開いておく理由はとてもシンプルで、「熱膨張による歪み」を避けるためです。
金属は温度変化によって微妙に伸び縮みします。マイクロメータの可動部であるスピンドルに、常に力がかかった状態(=測定面が完全に閉じた状態)で保管してしまうと、温度の変化によって内部に応力が溜まり、徐々に変形するリスクが出てくるんです。
この変形はわずかなものでも、0.001mm単位で精度を求めるマイクロメータにとっては致命的になることも。最悪の場合、測定値に明確なズレが出てしまい、寸法不良を見逃す原因になります。
ノギスとは違って、マイクロメータはこの「開いた状態で保管する」というひと手間が非常に重要です。使い終わったら、測定面をわずかに開いた状態にしてから、クランプせずにケースへ入れるのが基本です。
クランプしてはいけない理由とは?
マイクロメータを使い終わったあと、スピンドルを固定するために「クランプレバー」を締めたまま保管していませんか?一見すると、部品が動かず安心な気もしますが、実はこれ、精度を損なう一因になるんです。
その理由は、ズバリ応力の蓄積。先ほどと同様です。
マイクロメータの構造上、クランプした状態ではスピンドルがフレームに強く押し付けられる形になります。そこに室温の変化が加わると、金属はわずかに熱膨張・収縮しますが、クランプによってその逃げ場が塞がれている状態です。
結果、内部には「応力」が溜まり、長期的にはスピンドルやネジ部の歪みが発生し、測定誤差といった不具合につながる可能性があります。
取扱説明書やメーカーのガイドラインでも、「クランプは保管時に使用しないこと」と明記されているのはこのためです。
保管前の清掃と防錆の手順
マイクロメータは、ただ測定して終わりではありません。使い終わった後のひと手間こそが、次の測定精度を守るカギです。保管前の清掃と防錆処理をしっかり行うことで、サビや精度の狂いを防ぐことができます。
以下は、私も長期保管の際は実践している基本的な流れです。
① 油分・ホコリの除去
まずは、乾いた清潔な布などで、表面の油やホコリをやさしく拭き取ります。布は繊維が残らないものが理想ですが、私は普通のウエス(汚れていないもの)を使っています。とくに測定面やスピンドルは、皮脂や加工油、粉塵が付きやすいため丁寧に拭き取りましょう。
② 防錆油の塗布
次に、防錆油を布に少量染み込ませて、マイクロメータ全体に薄く塗布します。このとき、測定面には直接たっぷり塗らず、あくまで軽く。この作業は毎日でなく、長期保管の前や清掃後で構いません。
③ 測定面を軽く開けた状態で収納
繰り返しになりますが、クランプは緩め、アンビルとスピンドルを1mmほど離した状態にしてから、ケースに収納します。これで余計な応力がかからず、材質の安定性も保たれます。
この一連の作業は数分で終わりますが、手を抜くとサビや変形の原因になるだけでなく、修理費用や再校正の手間も発生します。
「あとでやろう」は禁物。1週間以上保管する場合はその場で、サッと手入れしておく習慣をつけましょう。
裸での保管はNG
「ちょっとした作業台の端に置いておけばいいだろう」――
そんな気持ちでマイクロメータを裸のまま放置していませんか?それ、かなり危険です。
マイクロメータは衝撃・湿気・ホコリ・直射日光など、あらゆる外的要因に弱い精密機器です。そのため、必ず専用の保管ケースや、引き出しの中など、外気の影響を受けにくい、安定した場所で管理することが基本です。
引き出しの中にしまう場合は、画像のようなスポンジクッションを使用するのがおすすめです。私の勤務先では、引き出しの中にこのクッションを敷き詰め、マイクロメーターの形に切り取って衝撃が加わらないように保管しています。



なぜ裸保管がダメなのか?
- ホコリの侵入でネジ部が摩耗 スピンドルの送りネジに微細なホコリや鉄粉が入り込むと、噛み込んでしまい、シリンダー部がだめになってしまうことがあります。特にペーパーなどの砥粒が入ると最悪で、一発で壊れてしまうこともあります。最新の注意を払いましょう。
- 不意の落下で精度ズレ 作業場で裸保管していたがために、うっかり落としてしまう事故も。マイクロメータは一度でもフレームが歪むと、再調整が必要になります。
- 湿気・日光による結露やサビ 特に高湿度環境では、空気中の水分が金属表面に結露し、サビの原因に。ケースに入れることで、湿気の侵入もある程度は防げます。
防湿もしておけばより安心
また、しっかりしたケースなら、防湿剤を一緒に入れておくことも一案です。これによって、内部の湿度を安定させることができ、より高いレベルでサビを防ぐことができます。
結論としては、裸保管は百害あって一利なし。どんなに高級なマイクロメータでも、保管状態が悪ければすぐに精度が悪化してしまいます。必ず専用ケースや引き出しなどに収納し、「測定→手入れ→保管場所に戻す」をルーチン化しましょう。
マイクロメータの置き場に適した環境とは?
保管方法だけでなく、「どこに置くか」もマイクロメータの寿命と精度を左右する重要なポイントです。
マイクロメータは、見た目以上にデリケートな精密機器。どんなに丁寧に清掃して、ケースに入れて保管していても、置き場所の環境が悪ければサビや精度のズレを引き起こしてしまいます。
たとえば、直射日光が当たる棚、エアコンの風が直接当たる金属棚の上、機械の振動が伝わる作業台の一角――
こういった場所は、すべて「避けるべき置き場」です。
ここからは、具体的にどんな環境がマイクロメータにとって安全なのか、どんな条件をクリアすべきかをひとつずつ解説していきます。
温度変化・湿度・直射日光は大敵
マイクロメータにとって、温度・湿度・光は“見えない敵”です。たとえ丁寧に保管していても、置き場の環境が悪ければ、精度の劣化やサビのリスクは避けられません。
温度変化:熱膨張による測定誤差
マイクロメータは、通常20℃の環境下での測定を基準として設計されています。温度が高すぎたり低すぎたりすると、本体の金属部が膨張・収縮してしまい、測定結果にズレが生じることに。
例えば、10mmの基準ブロックを測ったつもりが、熱膨張の影響で「10.005mm」などという誤った数値を表示することも。鋼材は10度変われば100mmのものが約0.012mmズレます。
精密測定の現場であれば、この差がいかに致命的なものかおわかりかと思います。
温度変化についてはこちらでわかりやすく解説しています!
直射日光:局所的な過熱で変形も
窓際や明るい照明の真下など、日光が当たる場所に放置するのも同様の理由でNGです。局所的な加熱により、マイクロメータの一部だけが膨張し、フレームや測定面に微細な歪みが出る可能性もあります。
湿度:サビの温床になる
湿度が高いと、金属表面に結露が生じやすくなります。特に梅雨時期や冬場の温度差がある環境では、ケース内にしまっていたとしても、内部で結露が発生し、目に見えないうちに腐食が進行しないともいいきれません。
湿度管理が甘いと、スピンドルや測定面にサビが浮き、操作性や精度に大きな悪影響を及ぼします。
結論:置き場は「空調の効いた、安定した室内環境」が理想
振動やホコリを避けるには?
マイクロメータを置く環境を整える際、意外と見落としがちなのが振動とホコリの存在です。これらも精度に大きな影響を与える、侮れないリスク要因です。
振動:じわじわと狂う「見えない破壊」
マイクロメータは、内部にラチェット構造や微細なスピンドルネジを備えており、これらは長時間の微振動でもわずかに摩耗したり、ネジ部が緩んだりすることがあります。
工場内でよくあるのが、振動のある旋盤やフライス盤の近くに工具棚があるケース。知らないうちに機械の振動が棚に伝わり、マイクロメータも少しずつ影響を受けている、ということが起こります。
大きい振動の起こる機械からは離して保管する、小さい振動の機械でも接する形は避け、直に振動が伝わらないように保管しましょう。
「置いてあるだけだから平気」と思っていても、実は振動の蓄積によって内部構造にズレが生じているということになりかねません。
ホコリ:見えない侵入者が命取り
測定面や送りネジ部にホコリが付着すると、操作時のスムーズさが失われるだけでなく、測定誤差の原因になります。さらにホコリは油分と結びついて粘着質になり、清掃が難しくなることも。
特に、グラインダーや研削機の近くでは、金属粉や研削ダストが飛散しているため要注意。これらは見た目に見えづらい上、静電気などでケース内にまで入り込むこともあります。
先項でも少し触れましたが、砥粒がマイクロメーター内に入ると最悪です。実際に経験があるのですが、スピンドルとシリンダーの間に噛み込み、傷を作ってしまい、まず砥粒が取れなくなります。なんとかヤスリ等で取れたとしても、バリが発生し、シリンダーにリーマを通すしかなくなる場合もあります。そうなればもう壊れたも同然。精密な測定は期待できません。
対策:静かな棚 × 密閉ケース が理想
振動対策としては、壁に接していない独立型の棚やキャビネットが理想です。棚の脚にゴムマットなどを敷くと、さらに効果的。ホコリ対策としては、密閉性の高いケースで保管し、使わない時はなるべく開けないことが重要です。
また、ケースを定期的に掃除したり、使用後に軽くきれいな布で拭くといったひと手間も精度維持につながります。
ケース内での湿度管理も忘れずに
「ケースに入れてるから大丈夫」と安心していませんか?
実は、ケースや引き出し内でも湿気の管理が不十分だとサビのリスクが残るんです。密閉されているからこそ、内部にこもった湿気が逃げ場を失い、結果として結露やサビの原因になることも。
ケースの中でも「湿気」は潜んでいる
特に梅雨時期や冬場の寒暖差がある場所では、ケース内外の温度差によって内部に結露が生じます。これが測定面やスピンドル部に触れると、サビの原因になることも。
また、作業中に開け閉めを繰り返すことで、空気中の湿気が入り込み、知らないうちにケース内の湿度が高まっていくという現象も起こります。
長期保管の対策は「除湿剤」と「定期チェック」
ケースに入れて1週間以上の保管を行う際は、油の塗布とともにシリカゲルや乾燥剤(使い捨てタイプでもOK)を一緒に入れておくのが効果的です。ポイントは、測定器に触れない場所に設置すること。
加えて、除湿剤は定期的に交換が必要です。吸湿しきってしまうと効果がなくなるため、目安としては1~2か月ごとに入れ替えると安心です。
ケースは保護だけでなく「環境づくりの一部」
とはいえなかなかここまでできないのが実情ですので、ここに書いたすべてのことができなくても、定期的な確認は行うようにしましょう。
保管ケースは、衝撃やホコリから守るだけでなく、湿度管理まで含めた「環境制御のための道具」と考えましょう。中が見えない分、定期的に開けて点検し、「わずかな錆びが浮いていないか?」を確認する習慣が大切です。
置き場に悩んだら?おすすめの保管場所例
「マイクロメータの置き場所、どこにすればいいのかわからない」
そんなときは、環境条件に合った保管場所の具体例を参考にするのが早道です。ここでは、現場でよく採用されている、マイクロメータに適した置き場を紹介します。
✅ 工具用キャビネット・パーソナルワゴンの上段引き出し
もっとも安心なのが、防振性のある工具用キャビネットです。中でもゴム足がついたタイプは振動の影響を受けにくくなっています。
私の勤務先では、防振性能はありませんが、サカエのキャビネットを使用しています。その引き出しにスポンジマットを敷くことで防振の代わりとしています。
また、可能であれば、エアコンの吹き出し口付近や窓際など環境変化の大きい場所には設置しないのが望ましいです。

✅ 空調完備の計測室 or 検査室
理想的な環境といえば、やはり恒温恒湿管理された計測室。20℃前後に温度が保たれている空間なら、マイクロメータの膨張・収縮リスクも大幅に軽減できます。
ただしこれはあくまで理想。私の働く現場のようにエアコン程度しかない環境では、せめて測定するものと測定器を同じ温度になじませる作業だけでも行うようにしましょう。
✅ 考慮すべきNG置き場
以下のような場所には絶対に置かないようにしましょう:
- 直射日光が当たる棚上
- 砥粒がでるグラインダーなどの近く(振動・粉塵が多い)
- 結露が起こりやすい鉄製ラックに直接置く
- 梅雨時期の換気の悪い倉庫内
保管場所に迷ったときは、「温度・湿度が安定」「振動が少ない」「清潔」の3条件を満たす場所かどうかをチェックするのがコツです。
🟦 まとめ|正しい保管と置き場管理でマイクロメータの精度を守ろう
マイクロメータは非常に高精度な測定器であり、その性能を最大限に活かすには「保管状態」が鍵になります。
たとえ使い方が正しくても、保管や置き場の管理が甘いだけで、サビ・変形・誤差といった問題が発生してしまうことがあります。
精密測定には保管状態が直結する
0.01mm単位の寸法を測るマイクロメータにとっては、わずかなホコリ・温度差・応力の偏りすら測定結果に直結します。
使い終わったら、必ず:
- 測定面を軽く開けておく
- クランプしない
- 1週間以上の保管では清掃・防錆を忘れずに
- 専用ケースや引き出しに入れる
この基本ルールを徹底するだけで、測定器としての信頼性は大きく向上します。
保管のクセをつければ長寿命・高精度を保てる
毎回のちょっとした手入れが、結果的にマイクロメータの寿命を大きく伸ばします。
「開ける→測る→拭く→戻す」の流れをルーチン化してしまえば、特別な努力をしなくても自然とベストな状態をキープできるようになります。
また、ケース内の湿度管理や、置き場の見直しも併せて行えば、精度面だけでなくトラブル回避にもつながります。
迷ったら、ケース&清潔&温度管理が基本!
どこに置こうか、どうしまおうかと悩んだら、とにかく次の3つを意識しましょう:
- 専用ケースに収納すること(裸は絶対NG)
- 清掃・防錆処理を徹底すること(汚れ・サビ対策)
- 温度・湿度が安定した環境に置くこと(直射日光や振動を避ける)
これらを守るだけでも、マイクロメータは「常に信頼できる道具」として、長く現場で活躍してくれます。
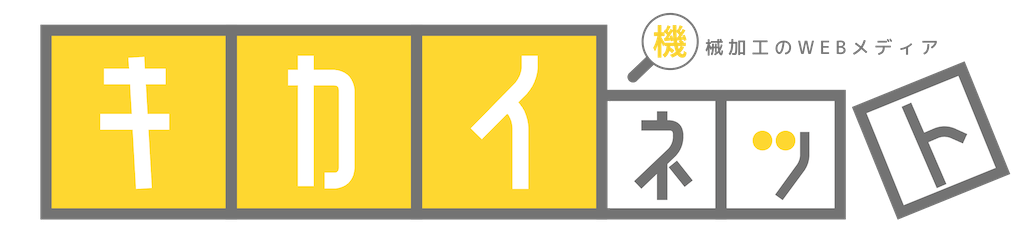
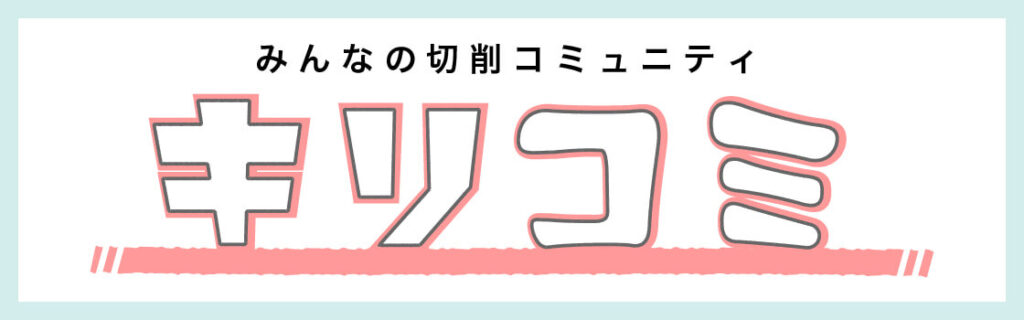
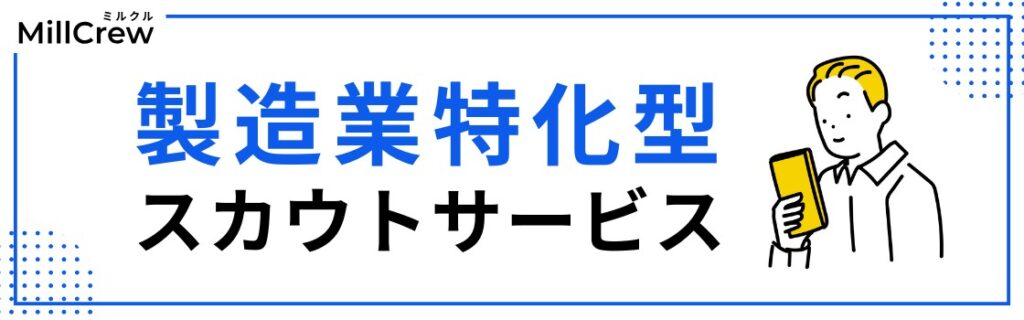

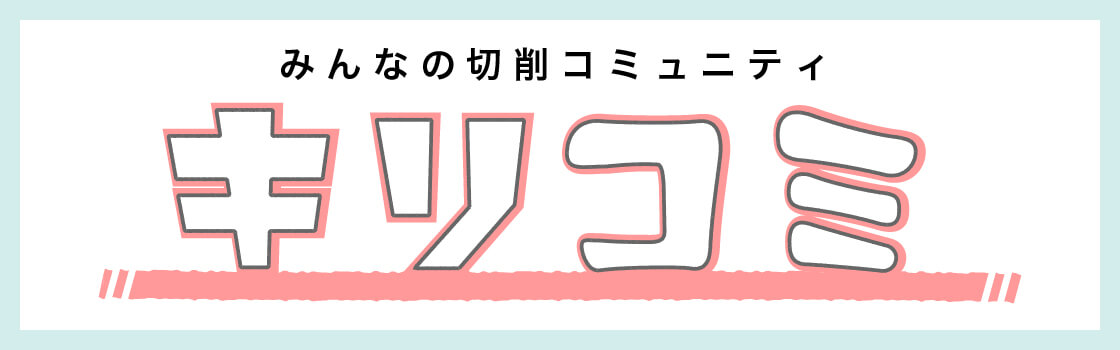
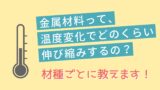


コメント